皆様お久しぶりです。
東京 保証推進事業部の江口です。
先日、新潟県に出張に行ってまいりました。
海産物や日本酒等、名産品がたくさんありまして、食の楽しみを満喫致しました。
新潟県といえば、「コメどころ」というイメージがあります。
確かに毎日頂いておりました炊き立てのご飯は美味でした。
ところで皆様は疑問に思ったことありませんか?
稲の原産地は温暖湿潤な地域なのに、日本では新潟~東北~北海道と寒冷な地域での稲作が盛んなのを?
答えは「寒冷地でも栽培可能なように品種改良を続けてきたから」です。
但し、近代以前は稲作が可能になっても、味覚に関しては現在の足元にも及ばなかったようです。
なぜなら今では嘘のようですが、昭和初頭の北陸米は<鶏(とり)またぎ米>といわれるほどまずかった、とされていたからです。
現在のような寒冷な地域でも栽培でき、害虫に強く、味も充分になったのは ある品種が出来てからです。
「水稲農林1号」 以下wikipediaより抜粋
≪1931年(昭和6年)、新潟県農事試験場で並河成資・鉢蝋清香により育成された。寒冷地用水稲であり、極早生種で食味もよく多収量品種であった。耐冷性を持つことで1934年(昭和9年)の東北地方の冷害での被害が少なかったほか、多収性を持つことで第二次世界大戦中・戦後の食糧生産に貢献した。このことにより、多くの人を飢餓や栄養失調から救ったとされる。
昭和6年の育成だが、並河らがこの品種を手がけたのは昭和2年、雑種5代の時からだった。交配地から送られた188系統から以後6年間をかけて選び抜き、最後に残ったのが農林1号である。その子孫からコシヒカリ・ササニシキなどの品種の交配親に用いられ、多数のイネ品種の祖先となっている。≫
現代でこれだけの偉業を達成すれば、国民栄誉賞ものだと思います。
並河成資・鉢蝋清香のお二人ともそれほど生前は名声も富貴も得ていません。
でもこの方たちの努力がなければ、私達は今 美味しいお米にめぐりあえてなく、食卓はずっと寂びしいものだったでしょう。
そんな事を思いつつ、今日もありがたくご飯をいただいています。



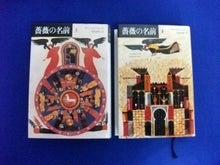

コメント